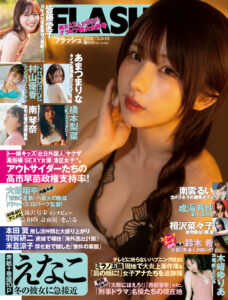倉野信次投手コーチ兼ヘッドコーディネーター(左)と話すソフトバンク・藤井皓哉
2024年7月に支配下昇格したソフトバンク・前田純投手に、1軍での登板チャンスが訪れたのは、9月29日のことだった。エスコンフィールドHOKKAIDOでプロ初先発のマウンドに立つと、6回を3安打無失点の好投。ヒットはすべてシングルで、二塁すら踏ませない快投ぶりで、プロ初勝利をマーク。
育成10位以下、つまり “育成2ケタ台指名” の投手が1軍で勝利を挙げたのは、ソフトバンクだけでなく、球界でも初という快挙だった。1軍チーフ投手コーチの倉野信次が「育成」の成果を強調する。
【関連記事:亀梨和也とYouTuberが変えた「野球の伝え方」スポーツ記者が「人間ドラマ」しか書かなかった “悪影響” とは】
「前田純に関しては “ファームの勝利” だと思います。育成からステップアップして、2024年はファームで10勝した。支配下登録されて1軍で勝利するわけですから。こうやって選手が伸びたのは、ファームのスタッフがしっかりと取り組ませてくれたお陰です。もちろん本人の努力もありますけど、素晴らしい結果だと思います」
■コーディネーター制を熟知する「魔改造コーチ」
1軍のチーフコーチでありながら、倉野はヘッドコーディネーターも兼務している。
米メジャー、特にマイナーでの選手育成の極意を知りたいと、単身渡米したのが2022年のことだった。倉野がソフトバンクの投手陣を預かった2016年からの6シーズンで、チーム防御率がリーグトップだったのは4シーズン。倉野の指導で球速が上がる投手が続出し、その手腕は「魔改造」の異名すら取ったほどだ。2017年からの4年連続日本一を支えた高いコーチング能力には、かねてから定評があった。
そのコーチの座を捨ててまで、倉野は渡米した。しかも当初は自費で、テキサス・レンジャーズ傘下のマイナー組織へ、最初はそれこそ “押しかけ入門” の形だった。
「僕が知らないことをまず見て、学んで、経験しようというのが第一です。それが体験できたのは、何よりも財産です」
そこで目の当たりにしたのが「コーディネーター制」だった。
「僕がアメリカにいる時から、(球団から)ヒアリングを受けていました。球団に戻ってくれ、という話ではなく『アメリカのコーディネーター制ってどういうものなのか?』と、編成部の人たちがアメリカに来て、ですね。見て、学んで、僕にも話を聞いて、去年(2023年の意)からコーディネーター制を本格的に始めました。その準備段階として、学びに来られていましたね」
「4軍制」が発足した2023年から、ソフトバンクは「コーディネーター」を新設している。チーム編成の最高責任者であるゼネラル・マネジャー(GM)を2019年から務めている三笠杉彦は、育成システムの「層の拡大」に伴う必然的な流れが、この「コーディネーター制」の導入だったと説明する。
三笠が「コーディネーター制」の重要性を知ったのは、メジャーからの “ヒアリング” だったという。コロナ禍の真っ只中にあった2020年から22年頃にかけ、海外からの日本への入国は厳しく制限されていた。それでも、メジャー各球団のGMたちは、日本の逸材たちを視察するために、来日する手段を常に探っていた。
そこで三笠のもとに、思いも寄らない “メジャーからの要請” が相次いだ。
「メジャー球団のGMから『日本に行きたいから、身元引受人になってくれないか』というリクエストが来たんです。他球団にも多分あったと思うんですけど、僕らはそれを結構積極的に、どんどんやろうと」
これを引き受ける代わりとばかりに、三笠は各球団のGMとの “勉強会” を申し入れた。
「マイナーで、いろんな軍やスタッフが多くなってくると、横の連携をどういう風にやっているのか、とか議論させてもらえないかと」
つまり、本場の育成システムの現状を教えてほしいと頼んだわけだ。メッツやパドレスは福岡まで足を運び、三笠にその現状をつまびらかにしてくれたという。彼らが強調したのが「コーディネーター」の存在だった。
■縦軸が「指導系統の統一」、横軸は「新分野の連携」
メジャー傘下のマイナーは、3A、2A、1A、ルーキーリーグに分かれ、さらにはドミニカ共和国に若手育成のアカデミーまで持っていたりする。こうした複層に「指導方針の統一」という、まず一本の軸を通さないといけない。これが「縦の軸」だと三笠は位置づける。
一方の「横の軸」は、昨今の野球界で増加傾向にある「新分野」の連携だった。データ分析、トレーニング部門、トレーナー部門など、これまでなかったような管轄分野が新設され、これに伴って携わるスタッフも必然的に増えていく。
しかもこうした新たな部門のスタッフは「元プロ野球選手」でない場合も多くなってきた。さらに野球界というのは、なぜかしら、プロ経験者でなければ発言力が小さかったりするような、実に同質性の高い、何とも不可思議な “村社会” という一面を持っている。
ここが、メジャーのGMたちも直面していた “新時代の難問” でもあった。つまり、それらの「縦」と「横」のもつれをほぐし、折り合いをつける役割が必要になる。
「それを解決するために、コーディネーターというのをものすごく重視して、たくさん置いているんだ、というのが、一様な答えだったんです」
三笠も、その “肝” が理解できたという。そこで2023年の「4軍制」発足にあたって、ソフトバンクも本格的に「コーディネーター制」を導入し、野手部門が関川浩一、投手部門が星野順治の、まずは投打2人体制でスタート。
2024年からは「会長付特別アドバイザー」を務めていた城島健司が「シニアコーディネーター」を兼任してコーディネーター全体を統括する役割についた。
倉野が投手コーチと兼任の形で「ヘッドコーディネーター」を務め、投手部門の星野、野手部門の関川に加えて、バッテリー部門が森浩之、野手統括兼守備走塁に荒金久雄の5人に増員。
2025年は、投手部門のコーディネーターを倉野、星野、元オリックス投手でロッテ、ソフトバンクで投手コーチを歴任した川越英隆が、野手のコーディネーターにも荒金、関川、森に、2024年は1軍外野守備走塁コーチだった井出竜也がそれぞれ加わっての7人体制へと拡充されている。
さらに4軍制の発足以来、S&C部門(ストレングス&コンディショニング)、メディカル部門、データサイエンスといった現場との関係性が深い部署では、それぞれのトップの肩書にも「コーディネーター」の役割が明記されている。
選手はそれぞれ、実力や経験に応じて、チーム内では「本籍」と呼ばれる1軍から4軍までの “クラス分け” がされているが、そのメンバーの入れ替えから、試合で打者に与える打席数、投手のイニング数の振り分け、さらにはウエスタン・リーグの公式戦に出場できる育成選手は5人と制限があるため、その抜擢メンバーを指名するのもコーディネーターだ。
フロントやコーディネーターが作成した育成プログラムに基づき、もちろん各軍の監督の意向を加味した上で、それらの “決定権” が委譲されている。フロントと現場という二頭立ての組織に、コーディネーター制が導入されることで、いわばトロイカ体制へと進化した新スタイルだ。
「アメリカだったら、1軍から7軍くらいまであるわけじゃないですか。それぞれのフロントと現場の通訳、橋渡しみたいな部分が大きいんですね。もう一つ、一番重要なのは、選手の指導方針の統一なんですよ。軍が増えれば増えるほど、指導者も増える。その各軍で指導者が違うこと、例えば真逆のことを言ったら、選手は迷いますよね。それが一番成長を妨げるということが分かっているわけですから、それを統一させることが一番の役割だと思いますね」
倉野が所属したレンジャーズでは、傘下のマイナー球団は3A、2A、1Aのヒエラルキー。シングルAはさらに「HIGH A」と「LOW A」の2階層に分かれ、その下にはルーキーリーグがあり、これも2階層に分かれている。つまり、メジャーを1軍、3Aを2軍と順々にあてはめれば「7軍制」になるわけだ。
これだけのカテゴリーで、レンジャーズならレンジャーズの「統一したやり方」というものがなければ、その階層を上がってきた時に、間違いなくハレーションが起こる。
私も、番記者時代にこんなやりとりを見聞きしたことがある。1軍と2軍で、教えられていることが違う。2軍から1軍に上がってきて、ブルペンで投手が投げる。「お前、2軍で何教えられてきたんや?」。また違うことを1軍で教えられ、直され、それで調子を崩したりする選手を何度も見てきた。
「2軍しかない日本のNPBですらそういうことが起こるのに、アメリカなんて、6軍、7軍くらいまであるから、そういうことがもっと起こり得るわけですよ。それを防ぐことは当然必要で、アメリカでは別に今始まったわけではない。
日本も2軍までしかなければ、なんとか調整できる。1軍と2軍、2つしか同じポジションはないわけですからね。でも、3軍を作った時に、これがより必要になる。4軍だったらもう、絶対に必要なわけですよ。要は指導方針を一貫したい。それが始まりなんです」
※
以上、喜瀬雅則氏の新刊『ソフトバンクホークス 4軍制プロジェクトの正体 新世代の育成法と組織づくり』(光文社新書)をもとに再構成しました。選手が主体的に成長する方法を徹底取材!
●『ソフトバンクホークス 4軍制プロジェクトの正体』詳細はこちら
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)