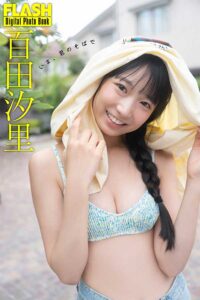写真はイメージです
保護観察官として加害者の更生を本分としながら、被害者の心情にも耳を傾け続けてきた一人に、法務省大津保護観察所長の西崎勝則(55歳)がいる。
保護観察所は法務省保護局が所管する機関で、犯罪や非行をした人の社会生活の中での立ち直りを指導・支援するほか、心神喪失者に対する医療観察制度を実施している。各都府県に1ヵ所、北海道に4ヵ所、全国に50ヵ所ある。
また、保護観察所には保護観察官が約1000人配置され、民間ボランティアの保護司とともに保護観察などを実施しているほか、約200名の社会復帰調整官が、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った精神障害者の社会復帰を促進している。
西崎が保護観察所の被害者担当官となったのは、保護観察中の加害者に被害者の心情を伝える、いわゆる「心情等伝達制度」をはじめとする、更生保護における犯罪被害者のための制度が始まった2007年12月のことだ。
保護観察所の「心情等伝達制度」の開始と同じ日に被害者担当官となった西崎は、制度が始まった直後に、以前から相談を受けていた交通事故で息子さんを亡くした被害者遺族の声をまとめ、加害者の刑期満了日に別の保護観察官への伝達を託した。制度を実施した第1号の保護観察官は西崎なのである。
保護観察所が担う「心情等伝達制度」の他に、被害者のためにかねてから設けられていた制度は3つある。
1つめは、「意見等聴取制度」。これは、刑務所や少年院からの仮退院や仮釈放を許可するか否かの審理を行う地方更生保護委員会に対して、被害者や被害者遺族が意見や気持ちを述べることができる制度だ。
2つめは、「被害者等通知制度」。検察庁からは、受刑中の加害者の収容区分や懲罰等の処遇状況、刑務所の所在地や釈放に関する事項などが、地方更生保護委員会からは、仮釈放審理を開始した期日や仮釈放についての審理結果などが、保護観察所からは、保護観察の開始年月日や終了予定年月日、保護観察中の特別遵守事項、保護観察官や保護司との接触回数などが、それぞれ通知されるというものだ。
私が見聞きした限りでは、被害者等通知制度は、大半の被害者や被害者遺族が申し込んで利用しているが、半年に一度程度通知される内容は、A4一枚から数枚の簡素なものであり、「反省している」「がんばっている」などの刑務所や保護観察所の職員の主観に基づく情報は通知されず、受刑中や保護観察中の状況のごく一部しか通知されないことから、不満を抱く利用者は多い。
3つめは、これらの制度に関する説明や関係機関へのつなぎなどを行う「相談・支援」である。西崎は、被害者担当官の任を離れた後も、多くの被害者遺族の相談を受け、制度等に関する豊富な知識をもとに、被害者が必要とする制度に関する情報提供や関係機関との橋渡しなど、制度としての相談・支援以上の取り組みを個人として続けている。
2023年12月には、刑の執行段階での「心情等伝達制度」がスタートしているが、保護観察中の「心情等伝達制度」とは、実施主体と対象が異なる。
保護観察中の心情等伝達制度は、仮釈放などにより保護観察となった加害者に対し、保護観察期間中に、保護観察所の被害者を担当する保護観察官(被害者担当官)が被害者から心情や要望などを聴取し、書面を作成した上で、加害者の保護観察を担当する保護観察官が加害者を呼び出し、これを朗読して伝達する。
「被害者担当官となるまで、私は、保護観察は、加害者の更生のためには、その人たちの問題のある部分も受け止めて寄り添うことだと考えていました。その考えは今も変わりませんが、他方で、目の前の加害者の更生を願うあまり、意識の中で、その向こうにいる被害者の存在を、どこか遠くへ追いやっていた自分がいました」(西崎)
西崎は、被害者担当官となったことを契機に、被害者遺族の集会に参加するなどして、犯罪被害に遭った人の実情や気持ちを直に知るようになる。
「衝撃でした。それまで味わったことのないものでした。被害者の声を聴けば聴くほど、加害者の更生に携わる立場だからこそ、被害者の声に耳を傾け、仕事に生かさなければならないと思うようになりました」
西崎は「かつては自分も、加害者に対して『すべてを忘れてイチから出直してがんばるように』と指導したことがあるんです」と吐露する。しかしそれは、被害者側から見れば反感しか湧かない。
被害者遺族の会に参加した当初は、自分が「加害者の支援側の立場」であることを明かすべきか迷い、話し合いの輪に入ることができなかった。しかしある時、自己紹介を求められ、「実は……」と恐る恐る名刺を差し出した。すると被害者遺族の一人から、「あなたみたいな人がこういう集まりに来てくれることが大事なんだよ」と歓迎の言葉をかけられた。保護観察官という刑事司法の行政官と犯罪被害当事者や遺族は、決して「対立」するものではなく、自分たちにできること、自分だからできることがたくさんあるはずだと肩を叩かれた、と気づきを得ていく。以後、行政官の知識を生かして犯罪被害者のさまざまな相談に応じ、次第に頼られるようにもなった。
「被害者の方々と出会ったことは衝撃でした。それまで味わったことのないものでした。私たち加害者の指導や支援に携わる者は、目の前の加害者の更生に思いをいたすあまりに、その向こうにいる被害者のことを、どこか遠くの存在として見ていました。
しかし、被害者の方々の声を聴けば聴くほど、加害者の更生に携わる立場だからこそ、被害者の声をきちんと聴いて、仕事にいかさなければならないと思うようになったんです。そのことを、被害者の方々から教えてもらったんです。被害者の方々の声を聴くことは、私のライフワークとなっています」
西崎は刑務所で始まった新制度「心情等伝達制度」に直接関与する立場ではないが、被害者と加害者の両方に接してきた身として、新制度を冷静に見ている。
「被害者にとって、加害者の指導を刑務所が行おうが、保護観察所が行おうが、国がやっていることに違いはないんです。新制度を利用することで、被害者が、加害者の贖罪意識が不十分だと思えば、その不満は国に向けられるのです。
また、新制度によって、加害者自身も、指導にあたる刑務官らも、被害者や遺族の思いを突きつけられます。そこで生じた課題を、今度は保護観察官が(加害者をどう更生させるかという)宿題として受け継ぐことになります。真に被害者のための制度とするためには、それぞれの役割をしっかりと果たしていく必要があります」
※
以上、藤井誠二氏の新刊『「殺された側」から「殺した側」へ、こころを伝えるということ』(光文社新書)をもとに再構成しました。被害当事者や遺族、そして加害者の「こころ」の一端を記録した渾身のノンフィクションです。
●『「殺された側」から「殺した側」へ、こころを伝えるということ』詳細はこちら
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)