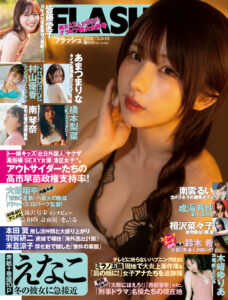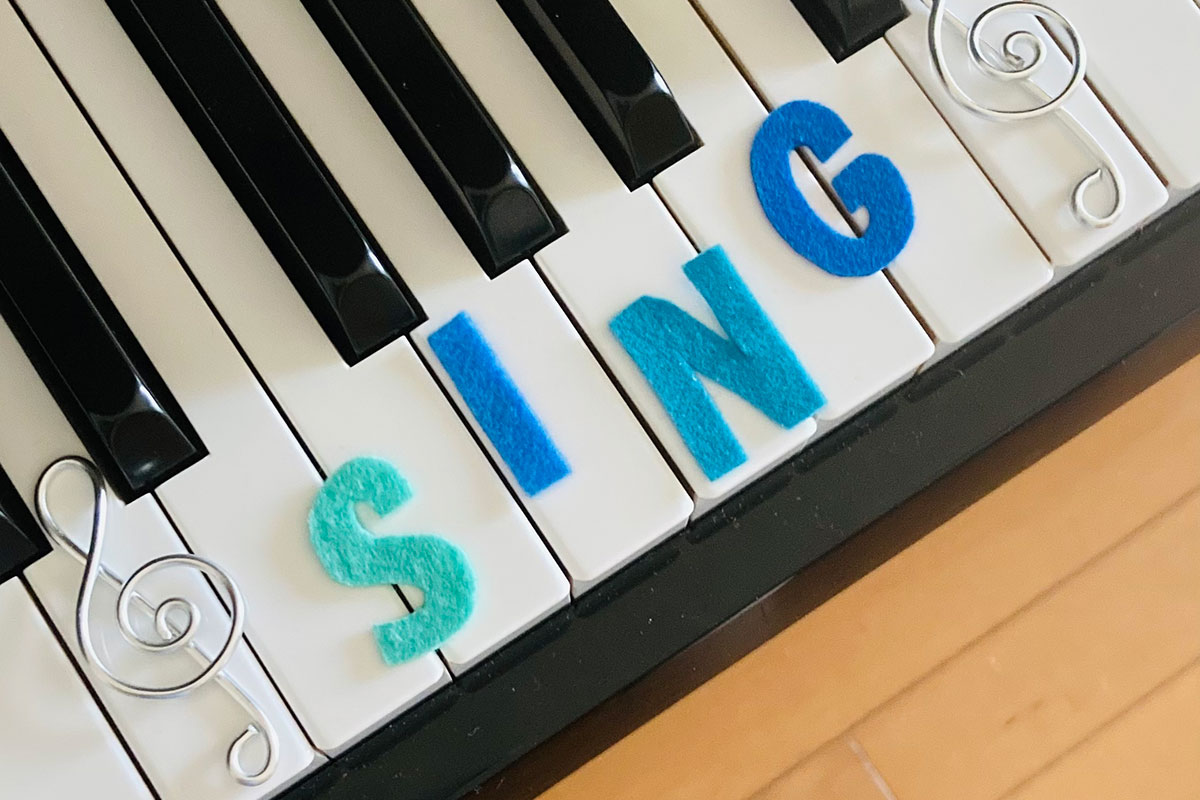
研究室のゼミで、学生さんが一本の論文を紹介した。数について考えるとき、空間のなかで数が並んでいるように感じる人達に関する研究である。
ある人はまっすぐな直線の上に数が並ぶ。別の人では途中で折れ曲がった線の上に数が並んでいる。さらに別の人では、途中で数字が上下ひっくり返ったりする。一人ひとりに決まった数の並び方があり、外界に重なって見えたり、心の中にはっきりと思い浮かんだりするのだという。
「何でこんな不思議な形が見えるんだろう?」と話していると、別の学生さんが「えっ、みんな見えるんじゃないんですか?」と発言した。そう、彼女は「共感覚」の持ち主だったのだ。
この出来事がきっかけで、私は共感覚について考え始めた。数が並ぶ不思議な形状を見て、これらの形を決めている何らかの原理が存在するに違いない、と確信したのである。
共感覚を持つ人は、ある特定の対象について考えたり、見たり聴いたりしたときに、それとは別の感覚を感じる。たとえば黒で印刷された文章を読むときに、文字に色がついているように感じる人がいる。あるいは、バイオリンのラ(A′)の音を聴いたときに、黄色い波が左から右に流れるように感じる人がいる。このとき、実際に見たり聴いたりする対象のことを誘発刺激、それによって喚起される感覚を励起感覚と呼ぶ。
共感覚者は、励起感覚が実際には存在しないことを知っている。それでも共感覚は消えず、自動的に喚起される。共感覚が邪魔になってしまうような場合であっても消えないという。
なぜ実際には存在しないものを感じるのだろうか? そして、存在しないと分かっているのになぜ消えないのだろうか? この謎は、共感覚を持つ人と持たない人では何が違うのかという疑問につながっている。
共感覚はとても多様である。たとえばSという文字から紫色を感じる人もいれば、青色を感じる人もいる。これは、Sという文字の形や発音だけによって共感覚色が決まるわけではないことを意味している。他の共感覚でもこれは同じで、ラ(A′)という音階から感じる色は、共感覚者によって異なっている。
共感覚者にとって、共感覚は当たり前の存在である。しかし、その感覚が生じなければならない理由はよく分からない。ある共感覚者は「safetyという単語は軽くバターを塗ったトーストの味、Phillipという名前はまだ熟していないオレンジの味」だと言う。別の共感覚者は「4は正直だけど3は信用できない、9は背が高く上品な紳士」だと書き残している。
■共感覚は何種類あるのか?
では、共感覚は一体何種類あるのだろうか?
英語圏の研究では、共感覚を誘発する刺激として、文字、単語、外国語の単語、人の名前、数字、曜日、月、声、痛み、触覚、姿勢、音楽、雑音、におい、味、色、形、感情、句読点や記号の19種類が知られている。
一方、励起される感覚としては、色、味、形、におい、雑音、音楽、触覚の7つの感覚に加えて、性別、性格、空間的配列などがある。
共感覚を持つと自認する人2789人を対象としたウォードとシムナーによる調査では、112種類の共感覚が確認された。この数は比較的厳密に見積もられているので、実際にはこれよりも多い種類の共感覚が存在するだろう。
一人で複数の種類の共感覚を持つことは珍しくない。この調査では、どの共感覚がどの共感覚と併発しやすいのかを調べることで、共感覚の分類が行われた。同じ人が持っていることが多い共感覚同士は発生のメカニズムに共通性があり、同じ人の中で共存することが少ない共感覚同士は共通性が少ないと考えられる。その結果、
(1)言語→色(数字→色、文字→色、曜日→色など)
(2)言語→味覚(単語→味覚、名前→味覚、外国語→味覚など)
(3)擬人化(数字→性格、数字→性別、文字→性格など)
(4)感覚の視覚化(音楽→色、感情→色、音楽→形など)
(5)空間系列共感覚(数字→空間、曜日→空間、文字→空間など)
(6)言語→触覚(単語→触覚、名前→触覚、外国語→触覚など)
(7)嗅覚/味覚(音楽→味、声→味、音楽→においなど)
(8)その他(聴覚→動き、音声→単語の視覚像、ミラータッチなど)
という、8つのまとまり(クラスター)が確認された。これらのまとまりをよく見ると、励起感覚が同じ共感覚が併発することが多いことが分かる。
■誰もが共感覚を持っている
繰り返すが、共感覚とは、ある刺激を見たり聴いたりしたときに、刺激そのものとは別の感覚を自動的に感じる現象である。この感覚は、本当に共感覚者だけが持っているものなのだろうか?
実はそうとも限らない。たとえば音の高さの感覚は、共感覚を持たない人であっても、共感覚に近い性質を持っているのである。
私達は音に「高さ」という性質があると感じる。一方物理的には、音の高さは周波数に対応している。周波数とは、1秒間に波が何周期あるのかを表す単位である。たとえば周波数が1000Hzの音では、1秒間に1000回、空気が振動を繰り返す。
ところで日本語でも英語でも、周波数が「高い」「低い」と表現する。ドイツ語やフランス語、アラビア語でも同じである。しかしよく考えると、周波数は1秒間に含まれる波の個数を表すので、「高さ」とは関係がない。物理的にはむしろ波の「多さ」に対応する。
しかし、多くの言語で「高い」「低い」という表現が用いられるのは、人間が一定時間内に含まれる波の周期が多い音を「高い」、少ない音を「低い」と感じるためだと考えられている。
なぜ多い方が高いと感じられ、その逆でないのかは、まだ十分に解明されていない。日常生活の中で聞く音を分析すると、上方からやって来る音の中に高い周波数の成分が多く含まれ、耳の形の特性によってその傾向がさらに強化されているという知見もある。また、脳の中に量と空間を対応付ける仕組みがあることが影響しているという説もある。
音の高さは、その他にも様々な感覚と対応している。高い音は、明るい色、小さいもの、尖った形と対応付けられやすいことが知られている。日本語では高い声のことを「黄色い声」と表現することがあるが、黄色は虹の七色の中でもとくに明るい色である。
スペイン語では高い声のことをvoces blancas(白い声)と言う。またドイツ語では低い音をdunkler Ton(暗い音)と言う。これらの例は、音の高さと色の明るさの対応が文化を超えて共通していることを示している。
※
以上、牧岡省吾氏の新刊『なぜ存在しない感覚が感じられるのか 共感覚の謎を解く』(光文社新書)をもとに再構成しました。音の色が見える、言葉に味がある、数字が宙に浮かんで見える…「共感覚」の謎を手がかりに「世界の見え方」の本質に迫ります。
●『なぜ存在しない感覚が感じられるのか』詳細はこちら
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)