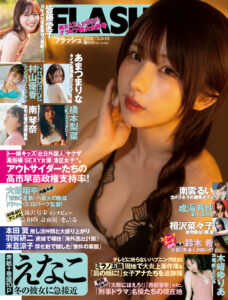日本人が幸せになれない、いちばん大きな原因は「愛していない」ことにある。多くの人たちが「愛すること」よりも「愛されること」を優先してしまっているのだ。ロングセラー『生きる意味』の著者・上田紀行氏が、生きる意味の核心である「愛」について提言する。
【関連記事:超遠距離恋愛だった「黒柳徹子」40年に及ぶ生涯最高の恋】
※
既婚者の恋愛が増えているとしたら、インターネットのSNSサイトの影響が大きいということは言えるでしょう。日常生活の範囲では出会えない人に出会えるという意味でも大きいし、別人格を使い分けられるという意味でもそうです。
不倫そのものは昔からあったはずですし、古今東西の文学に不倫は格好の題材として数多く描かれています。
しかしこれまでの時代には、「もしバレたらここにはいられない」という危機感や背徳感もあり、小説を読んで憧れるけれども危ういところで実行に移さない、ということもあったのではないかと思います。
しかし、「ネットとリアルの2つの世界は抵触しない」という自覚は、行動を大胆にします。多くの人が、インターネット上でいくつものハンドルネームやアカウントを持つことに慣れているので、
「この場ではこういう私だけど、家庭の中の私とは違う」
「フェイスブックではこう書き、子どものPTAのLINEではこう書き、彼へのメールにはこういうふうに書く」
と、人格を使い分けることへの罪悪感もなくなっているのかもしれません。
「家には持ち込まないからいいじゃない」という話になるとすると、それをどう考えるかということにはなります。
以前、NHKの「クローズアップ現代」という番組で出会い系サイトを特集し、スタジオでそれらの事例にコメントをしたことがありました。そのときディレクターが取材してきたのが、次の4つの体験談でした。
1番目は、パソコンを使った出会い系サイトで結婚までたどり着いたという典型的な成功事例。理系の大学を出て地方の研究所に配属された男性が、口下手でまったく出会いがない。
それで出会い系をやってみたら、同じようにシャイで、自分の容姿に自信がないので外にも出て行きたくないという引っ込み思案な女性とつながった。彼らは何か月間で数百通のメールを交換し合って、めでたくゴールインできたというものです。
ところが2番目は、同じようにメールで気が合って、一日に何十通もやりとりしてかなり盛り上がったので会ってみたら、その男性はあまりタイプではなかった。
それで断ったのですが、彼はそのとたんにストーカーになってしまいます。家にまで押しかけられ、最後にはレイプされて男性不信になってしまったという悲しい事例でした。
3番目は、サラリーマンが会社のパソコンからひたすら出会い系サイトにアクセスしてしまい、上司にバレて注意されてもやめなかったので、とうとう解雇になったという情けない事例。
インタビューでディレクターが「なぜ会社からやったのですか」と聞いたら、「だって、パソコンの向こう側に女子大生がいるんですよ。やめられませんよ!」と、まったく懲りていなかったのです。
4番目は、大変興味深いものでした。女性は子育て中のお母さんで、VTRでは子どもをブランコに乗せながら、ひたすらケータイメールでその人と会話をしているのです。
相手の人はすぐ返事を返してくれて、しかもまるでかゆいところに手が届くような、気持ちのピッタリ合ったやりとりができる。ただし、当時は「メールやり放題」ではなく従量制だったので、この女性は月に10万円ぐらいかかってしまい、大問題になってしまったという事例でした。
このとき、女性が言っていたのは「これだけ話が通じて、会話のツボがかみ合うのなら、もう会わなくてもいいよねってお互いに言い合っているんです。たとえ、相手が人間じゃなくて人工知能であってもいいって言い合ってるんですよ」という発言でした。
「出会い系サイト」なのに、本人同士は「出会わなくてもいい」と言っているのです。これは「出会ってイメージが壊れてしまったら元も子もないから」という不安から逃げているのかもしれません。
それでも、「人工知能でもかまわない」というのは、魂の部分で直結しているので、生身の人間である必要すらないということになるのです。
「これはまさに、究極型ですね」と感動してディレクターと話をしていたのですが、残念なことに「人工知能でもいいという言葉の意味が、視聴者に伝わらないのではないか」というプロデューサーの判断で、VTRのこの部分はカットになってしまいました。
「出会い系サイト」とはいったい何か。犯罪やら現代の猥雑なものやら、いろいろなものを包み込みながらも、なぜ広がり続けているのか。
そこには人々の、「私を深いところまで承認してくれる人はどこにいるのだろう」という非常に大きな問いを抱え込んでいるのではないか。
このことを見せるという意味では、あの「人工知能でもよかった」という発言は、衝撃的なほどその構造を見せていたはずです。そこで視聴者に問われるのは、「それだけ自分自身を深く承認してくれるという対象が、あなたたちにはいますか」ということになったはずです。
※
以上、上田紀行氏の新刊『愛する意味』(光文社新書)を元に再構成しました。
『愛する意味』詳細はこちら。
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)