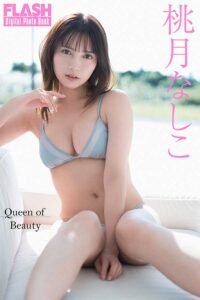みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏
■下落率はアルゼンチン・ペソと同程度
「円安のメリットを享受するのは、基本的にグローバルな輸出製造業です。外国に対して安くモノを売れるし、売り上げもかさ上げされる」
みずほ銀行チーフマケット・エコノミストの唐鎌大輔氏は、こう分析する。
「海外への投資の利益も円建てでたくさん入ってくるわけです。一方、円安のデメリットを被るのは、内需依存型の中小企業と、物価上昇の影響が直撃する家計です。
さらに、日本では長らく給料が上がっていないので、実質賃金は下がっていく。このまま円安が続けば、富める者とそうでない者の二極化が進みます」
当然ながら、円安にはメリット、デメリットの両方がある。問題は、今回の円安が進行するスピードがあまりに速かったことだという。
「今回、1ドル=110円台から130円台になるまで3カ月もかかっていません。企業は円高にしても円安にしても、常に為替予約をしてリスクヘッジしていますが、今回のような急激な変動ではヘッジが効かない。
すると当然、経営計画はブレる。その意味では、企業にとっても“悪い円安”です。日銀自身も急な変動はよくないと言っています」(同前)
現在の円安は、日米の金利差により生じていると説明されることが多いが、原因はそればかりではないという。
「金利差だけが原因なら、ほかの通貨も円と同じくらい下がっていなければならないわけですが、円だけが突出して弱いのです。2021年初めから足元までの通貨の下落率を見ると、円はアルゼンチン・ペソと同じくらい下落しています。それより下がっているのは、トルコ・リラくらいです」(同前)
先進国である日本の円はなぜここまで安くなったのか。
「“日本売り”の要素もあると解釈しなければ説明がつきません。日本は貿易赤字が拡大して、回復する目途が立っていない状況。成長率を見ても、先進国の中で、日本だけがコロナ前の水準に戻っていない。そんな日本経済は評価できないと、海外は見ている。つまり『日本は買えない』のです」
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)