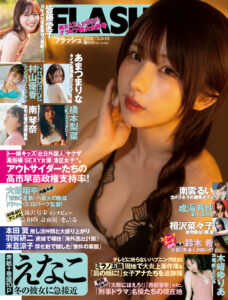明石昌夫さん(本人提供)
B’z、TUBE、ZARD、WANDS、大黒摩季、DEEN、T-BOLAN……。1990年代、「ビーイング・サウンド」が日本の音楽チャートを席巻した。
音楽プロデューサーの長戸大幸氏率いる音楽事務所「ビーイング」(現・B ZONE)は数多くのアーティストを発掘し、ビッグヒットを連発した。そのサウンドの礎を作ったのが、音楽プロデューサーの明石昌夫さん。「3人目のB’z」と呼ばれる存在だった。
その明石さんが、5月19日、亡くなった。68歳だった。死因は非公表。本誌は、2025年1月7日、明石さんに90分の独占インタビューをおこなっていた。生前最後となった肉声を、未公開エピソードを中心に紹介する。
――明石さんがB’zのアレンジャーとして関わるようになったきっかけから教えてください
30歳で上京して、僕を拾ってくれたのがビーイングでした。当時、事務所内でB’zの企画が立ち上がっていて、僕はアレンジャーとして参加することになりました。長戸さんがアレンジャーを探していたんです。
【関連記事:「乙女の心臓撃ち抜く凶器」B’z稲葉、還暦前に “超イケオジ” 化…anan表紙に集まる歓声、“オバ化” 懸念する声も】
――それまで、アレンジャーとしてのキャリアは?
まったくありません(笑)。僕が作ったデモテープを長戸さんが聴いて、「アレンジしてみないか?」と。僕は、作詞家でも作曲家でもシンガーでも音楽に携われればよかったので、やることになったんです。ただ、最初の1、2年は本当に大変でした。僕の人生でいちばん大変な時期でした。とにかく、やってもやってもボツなんですよ。僕がアレンジして、スタジオミュージシャンを集めて、スタジオでレコーディングして、最初の20曲ぐらいボツだったんです。これ、レコード会社の発注だったらありえない。数百万単位のお金をかけているわけですからね。
――B’zとの最初の出会いは?
1987年、1stアルバムが出る1年ほど前になります。2人とは会社で顔を合わせたことがある、という程度でしたね。松本(孝弘)さんはスタジオミュージシャンだったので、何度かギタリストとして参加してもらっていました。すでに売れっ子で、TM NETWORKや浜田麻里さんのサポートをやってました。ギタリストの北島健二さんの次を担う、若いハードロック系のスタジオミュージシャンという位置づけでしたね。稲葉(浩志)さんは、ビーイングのボーカルスクールに通っていて、優等生でした。
――どんなふうにレコーディングは進んでいったのでしょうか?
基本的には、松本さんがドラムやシンセのパターンを作ってきて、アルバム9曲のうち6、7曲かな。細かいことは覚えてないけど、半分以上の曲を打ち込んできて。その音色を差し替えるのが僕の仕事だったんです。だから最初は「マニピュレーター」でした。僕が音を足すことは、ほとんどなかったんです。ドラムのフィルを入れるぐらいだったと思いますね。少しベースラインをいじったかもしれないけどそれぐらいかな。松本さんのデモテープの段階で、曲の世界観は完成されていました。
――制作中、「これは売れる!」という感触はありましたか?
僕と松本さんの間では、最初から絶対に売れると思っていました。稲葉さんは歌がめちゃくちゃうまくて、声質がよくて、リズムがよくて、かっこよくて……おまけに高学歴(笑)。松本さんのギターの音は、当時、僕が唯一認めていたサウンドでした。
――松本さんは、小室哲哉さんのサウンドに大きく影響を受けていたそうですね
サウンドに限らず、メロディーの作り方やプロモーション戦略なども含めて、小室さんから影響を受けていました。以前、松本さんと飲みに行ったとき、「B’zが売れたのは小室さんの理論が正しかったことを証明したにすぎない」って言っていたほど。曲づくりについては、小室さんから「メジャーの曲は暗く、マイナーの曲は明るく。メロディはわらべ歌のようにわかりやすく」と教わったそうです。B’zの楽曲をゆっくりと、小さな声で歌ってみてください。たしかに、わらべ歌みたいになるんですよ。
――レコーディングで音源を差し替えるマニピュレーターからアレンジャーも兼務するようになったのは?
松本さんのデモテープのなかにまだアレンジされていない曲があって、松本さんに「明石君はアレンジャーなんだから、最後の2曲をアレンジして」って言われて作ったんです。それを聴いて、「次のアルバムからは明石君に頼むからね」って言われて「おー、やったー!」って(笑)。嬉しかったですよ。
――ちなみに、その2曲とは?
『Nothing To Change』というバラードと、1stシングルの『だからその手を離して』。このときのアレンジのスタイルが、のちの「ビーイング・サウンド」になっていきます。
――B’zは、ヒットするまで少し時間がかかりました
「もうすぐ売れそうだ」と言われるけど、「なんか伸びないね」っていう感じが、セカンドアルバムまであったんです。そこで、レコード会社のスタッフに、「売れることを度外視して、肩の力を抜いて遊んでください」と言われて、「よしやってやろう! 究極のユーロビートハードロックを作ろう」という姿勢で完成したのがミニ・アルバム『BAD COMMUNICATION』で、これがヒットしたんです。2人はユーロビートとハードロックが大好きだったんです。稲葉さんの「LOUDNESS好き」は有名だったし、松本さんは当時ヒットしていたバナナラマの『I Heard a Rumour』のイントロを、家の留守電の音にしていました(笑)。
――アレンジャーの名前が変わっても、ビーイングのアーティストのサウンドは一貫したものに聴こえました
長戸さんに、「派手にしろ」「インパクトが大事」と言われていたのと、あと「今はB’zの評判がいいから、(サウンドは)全部B’zにしろ!」って言われていて。ぜんぶ同じに聴こえるのは、意図的なんです。
――明石さんのサウンド作りの骨子になる部分を、ほかのアレンジャーが踏襲していた?
そうです。というか、させられてます。長戸さんに「明石のアレンジを聴いて、そのとおりに作れって言われたんだよ」って、別のアレンジャーから聞いたことがあります。
――B’zのレコーディングで、いちばん楽しかったことは?
『BE THERE』(1990年)のイントロですね。じつは、あのインパクトの強いイントロは最後にできたんです。最終的に仕上げる段階で、松本さんと稲葉さんがスタジオにいなくて、僕一人で作ったんですよ。ボビー・ブラウンの『Dance!...Ya Know It!』というリミックスアルバムがめちゃくちゃかっこよくて、いろんなところをサンプリングして作ったのがあのイントロ。僕が好き勝手に作って、撮影が終わって帰ってきた2人に「こんなのできたよ」って聴かせたときに、松本さんがびっくりしてて(笑)。口開いてたような気がしました。あっけにとられたみたいな。後で聞いたんですけど、「これを世の中に出すべきかどうかを悩んだ」って言っていました。「この世界を、みんなが理解できるんだろうか?」と悩んだそうです。
――B’zは、音楽界でさまざまな記録を打ち立てています。その理由をどう分析されますか?
それは、松本さんがすべてです。作曲ができてギターが弾けるだけでなく、プロデューサーとしての才能にも長けている。ビジネスマンとして優秀なので、仮にギターが弾けなくても成功する人ですよ。また、松本さんは人の意見を否定しません。包容力があって、聖徳太子の「和をもって貴しと為す」の人。そんな人は、松本さんしかいません。極論を言えば、バンドに松本さんがいるか、いないか、なんですよ。
J-POPの歴史を彩った数々のアーティストのアレンジを手がけた明石さん。1997年までB’zのサポートメンバーとして、ベースとマニピュレーターを担当した。その後は音楽プロデューサーとして活躍し、洗足学園音楽大学教授として多くの才能を育ててきた功労者の冥福を祈りたい。
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)