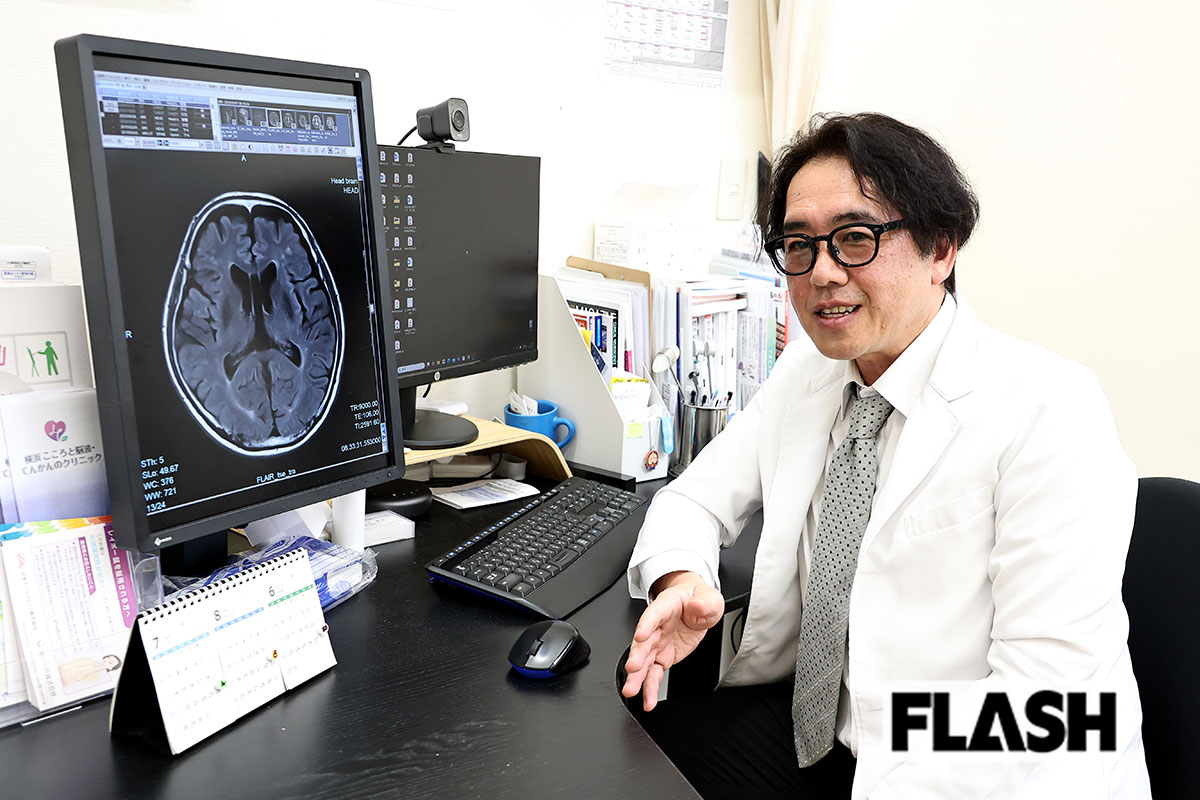
「えびな脳神経クリニック」の尾﨑聡理事長(写真・長谷川 新)
「脳の血管病全般をいう『脳卒中』は、“冬の病気”と思われがちです。たしかに、脳の血管が破れる『脳出血』は、寒さによる血圧上昇や、室内外の温度差によるヒートショックが原因であるケースが多く見られます。しかし、血管が詰まって起きる『脳梗塞』は、夏にも冬と同程度、発症しているんです」
そう語るのは、神奈川県海老名市の「えびな脳神経クリニック」理事長で、脳神経外科専門医の尾﨑聡医師だ。
国立循環器病研究センターの調べでは、脳梗塞の発症率は冬(25.6%)と夏(25.5%)で均衡している。
【関連記事:DJ KOO、9.8ミリの脳動脈瘤「首を切って血を逃がす」7時間の大手術を乗り越えた「医師のひと言」】
「夏は発汗によって体内の水分と塩分が排出され、血液がドロドロになり、血栓ができやすくなります。さらに暑さで血管が緩み、血圧は下がりがちです。
脳梗塞は“血圧が急に上がって起こる病気”というイメージが強いでしょうが、実際には血圧が下がったときにも発症します。血圧が下がると血液を押し出す力が弱まり、ドロドロした血液で血管が詰まってしまうのです」(尾﨑医師、以下同)
尾﨑医師のクリニックを訪れた50代男性は、前夜に深酒をし、冷房を使わずに就寝して大量の寝汗をかいた翌朝、フラつきが続いたという。MRI検査の結果、小さな脳梗塞が見つかった。
「この方は脱水、飲酒、就寝中の低血圧という“夏のトリプルリスク”が重なった典型例です。本人は『二日酔いだと思った』と言っていましたが、そのまま放置すれば大きな脳梗塞につながっていた可能性があります」
■熱中症と似た症状で発見が遅れてしまうことも
脳梗塞は、突然、発症するケースに目を奪われがちだが、症状がじわじわと進行することも多い。
「年齢のせいかな、と体の異変を見過ごしてしまう方は少なくありません。怖いのは、その間も脳のダメージが進んでいることです」
ある60代男性は、片目の視界がスッと暗くなったため眼科を受診したが、異常は見つからず経過観察に。しかし、そのわずか2日後、自宅で倒れて尾﨑医師のもとに救急搬送された。これは数分で視野が戻る「一過性脳虚血発作(TIA)」と呼ばれる、脳梗塞の重大なサインだった。
また、何もないところで転ぶことが増えるのも危険信号だという。
「脳梗塞で救急搬送された患者さんが、その1カ月くらい前から、たびたび転んでいたというケースはよく見られます。夏場の場合、めまいなど熱中症と似た症状が現われるため、発見が遅れてしまうことがあります」
兆候にはほかにも、「ろれつがまわらない」「言葉が出てこない」「片側の口角が下がる」「片側の手足がしびれる」などがある。
有名人の例も多い。2021年に爆笑問題の田中裕二が脳梗塞で入院したときは、「一瞬だけ左の手足が動かなくなった」と、自覚症状をラジオで語っている。Mr.Childrenの桜井和寿は2002年、ツアー中に軽いフラつきと視界の異常を訴え、小脳梗塞であることが判明して活動を休止した。
こうした有名人の事例からもわかるように、兆候はすぐに収まり、また日常的に起こりうる症状であることが多い。そのため「疲れ」や「寝不足」、「夏のストレス」のせいだろうと片づけられやすいのだ。尾﨑医師が続ける。
「視界が一部欠ける、物がぼやけて見えるといった症状は、脳の血流障害が原因の場合もあります。眼科で異常なしとされ、その後に脳梗塞と診断される例は少なくありません。
言葉が出てこない、昨日のことを思い出せない、同じ質問を何度も繰り返すなどの場合も、『年のせいかな』と片づけるのは避けましょう。急にもの忘れが増えた場合は、脳の一部で血流が滞っている可能性があります。
食べ物や飲み物がうまく飲み込めず、むせることが増えたというケースも見過ごされやすいのですが、脳梗塞の初期に出る症状のひとつです」
■遅れれば遅れるほど後遺症が出る可能性が高くなる
首の異変も見逃せない。
「50代男性で、左側の首が痛くて眠れないと整形外科に通っていた方がいました。鎮痛薬が効かず、フラつきが出始めた段階で当クリニックで精査すると、解離性椎骨(ついこつ)動脈瘤から起きた小脳梗塞でした。
椎骨の動脈解離は、血管の内壁の剥がれた部分に血栓ができやすくなります。早期発見と治療が不可欠です」
実際、2022年に千鳥のノブが「右椎骨動脈解離」で1カ月の休養を余儀なくされた。くも膜下出血や脳梗塞とは紙一重だったといえる。いずれも一見、バラバラな症状だが、脳の一部がダメージを受けているサインかもしれないのだ。
「それらの症状が短時間で回復しても、“もう大丈夫だ”とは思わないでください。脳梗塞は発症後の時間との勝負です。発症から4.5時間以内に血栓を溶かす治療が始められるかどうかで、その後の生活の質は大きく変わります。
一命を取り留めたとしても、治療が遅れれば遅れるほど、手足のまひなどの後遺症が出る可能性は高くなります」
生活習慣のなかにも脳梗塞の危険は潜む。糖尿病や脂質異常を放置したり、睡眠不足など生活リズムが乱れたりしていては、発症リスクを高めてしまう。過労、喫煙の習慣などにより、30~40代でも脳梗塞は起こりうる。前出の桜井も、32歳で発症している。
■フラつき、だるさが取れない場合は医師に相談を
「水分をあまり取らない人は、今日からでも、寝る前と起きた後にコップ1杯の水を飲む習慣をつけましょう。アルコールは代謝される際に体の水分を奪い、脱水を引き起こすため、かえって脳梗塞のリスクが高くなります」
飲むなら、血圧を変動させにくい常温の水を。血圧管理は、脳梗塞の予防の基本だからだ。
「高血圧の方はもちろんですが、冒頭でお話ししたように、血圧が低すぎる場合も脳への血流が不安定になり、脳梗塞リスクがむしろ上がるのです。とくに、収縮期血圧(上の血圧)が100を下回る状態が続くと要注意です。
高齢でもともと低血圧の方、降圧剤で下がりすぎている方はとくに注意してください。自宅で朝晩の血圧測定を習慣にし、フラつきや朝のだるさが取れない場合は、医師に相談しましょう。血圧は低ければいいというものではなく、適正な範囲を保つことが大切です」
そして尾﨑医師は、「生活習慣病のある方は、症状がなくても1、2年に1回のMRI検査をおすすめします」と訴える。
「MRIで、過去に小さな脳梗塞を起こしていたことを初めて知る方は少なくありません。こうした症状のない“隠れ脳梗塞”を持つ人は、脳梗塞の再発リスクが4倍になるといわれています。季節や年齢に関係なく、今日から脳を守る生活を始めてください」
体のわずかな異変で病院に行く“勇気”が、未来の自分を救うのだ。
取材/文・吉澤恵理(医療ジャーナリスト)
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)







