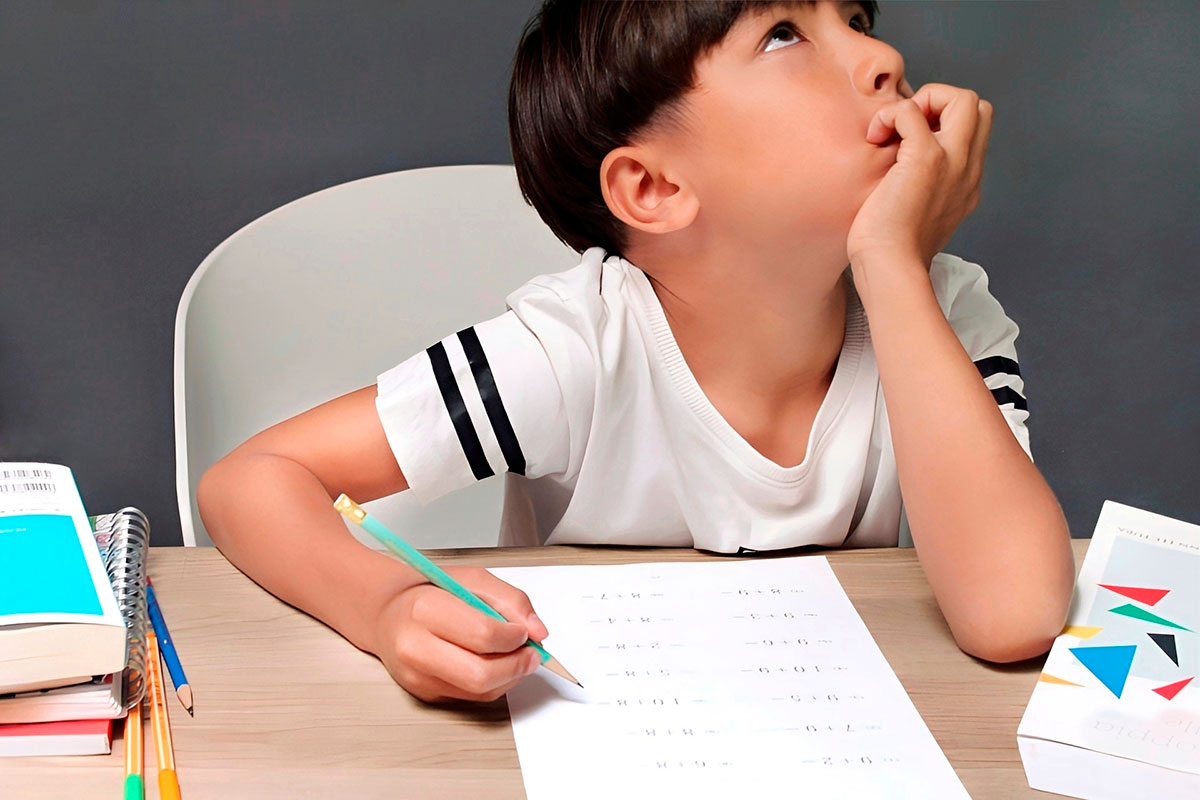
「鎌倉幕府ができたのは1185年? 昔は1192年で『“いいくに”つくろう』と暗記したのに……」
現在の小学生の教科書を見て「違い」に戸惑う大人たちは多いだろう。
「ほとんどの教科で違いが見られますが、とくに多いのは社会科です。歴史の検証が進むにつれて、これまでの解釈とは違っている部分が判明するため、教科書の表現も検証結果に合わせるようにしているのです」(塾講師)
教育評論家の親野智可等(ちから)氏も「歴史学や考古学の研究は日進月歩で、毎年、新しい発見があります。それに従い、教科書も変更されます。理数系の研究においても同様で、国際基準が変わることもあります。冥王星も『惑星』とされていましたが、現在では『惑星』とはなっていません。リットルの『L』への表記変更や『pH』の読みなどもそうです」という。
表現が変更されることで、教師など教育現場に戸惑いは生じないのだろうか。
「先生たちは、自分たちが学んだものが身についているので、変更のたびに戸惑うことになると思います。先生たちにはつねにアップデートが求められます」(同前)
学校現場だけでなく、家庭学習も変わってきている。いまや宿題の丸つけをするのは教師ではなく、保護者が主流だ。親野氏は「子どもが問題を解いたら、できるだけ早く丸つけをしたほうが教育的効果は高い」と指摘する。
「すぐに丸をもらえばモチベーションアップにつながり、間違えてやり直す場合も、子どもの頭のなかにメモリーが残っているので、ゼロスタートにならず、負担が少ないのです。ご家庭の事情にもよりますが、保護者に丸つけと採点をしてもらえば先生の負担も減ります」(同前)
■「令和の教科書」 書き換えられた!」
【国語】
・(昭和)松尾芭蕉の紀行文は「奥の細道」 → <令和>「おくのほそ道」
・(昭和)「徒然草」の作者は吉田兼好 → <令和>卜部兼好(うらべかねよし)または兼好法師
■「近年では歴史的事実や、人物本来の名前を尊重する傾向が強まっています。そのため、松尾芭蕉直筆の表紙に記されている『おくのほそ道』へ変更されました。吉田兼好は卜部氏の出身で、当時の記録では卜部兼好、または出家後の兼好法師で表記されています」(親野氏、以下同)
【算数】
・<令和>繰り上げ・繰り下げは「さくらんぼ算」で計算する
■「文部科学省の学習指導要領では『さくらんぼ算』という名称は使われていませんが、計算の考え方として、2010年前後から授業に取り入れられるようになりました。数の仕組みは10進法に基づいているので、『10のかたまり』を作るのが基本になります。暗算では見えにくい計算の過程が図示できます」
【理科】
・(昭和)冥王星は惑星だ→<令和>冥王星は惑星ではない
■「国際学天文学連合が2006年に、新しく惑星の定義を導入しました。新しい定義では、惑星は(1)太陽のまわりを公転している(2)自らの重力でほぼ球形である(3)軌道近くでほかの天体を排除している、という条件をすべて満たしている必要があります。冥王星は(3)を満たしておらず、『準惑星』として分類されることになりました」
・(昭和)水素イオン指数をあらわす指標はpH(ペーハー)→ <令和>pH(ピーエイチ)
■「アルカリ性、酸性などを示す水素イオン指数のpHは、ドイツ語読みで『ペーハー』でした。1957年に日本が国際単位系に合わせて英語読みの『ピーエイチ』に統一する方針を採用し、JIS規格でも『ピーエイチ』と読むことが定められました。2008年の学習指導要領改訂の結果、読み方が明記され、『ピーエイチ』が定着しました」
・(昭和)遺伝には優性遺伝、劣性遺伝がある → <令和>顕性遺伝、潜性遺伝がある
■「2021年度の教科書から『メンデルの遺伝の法則』に登場する優性・劣性遺伝の表記が、顕性・潜性遺伝と改訂されました。優性・劣性の表記は遺伝の特徴にすぎないのに、優劣があるような誤解を招くとして日本遺伝学会などで見直しの動きが進んでいました。それが反映された形です」
・(昭和)哺乳類は、爬虫類から進化した → <令和>両生類から進化した
■「哺乳類は爬虫類から進化したと考えられてきましたが、最近の研究成果から、両生類から進化して陸に上がった四肢動物の単弓類が哺乳類の祖先だと考えられるようになりました。そこで、2012年度以降の教科書から、哺乳類のルーツが両生類であると表記されるようになりました」
・(昭和)実験でアルコールランプを使う → <令和>カセットコンロを使う
■「アルコールランプは小型で倒れやすく、炎が見えにくいため周囲のものに引火するなど、授業中の事故が絶えませんでした。そのために登場したのが、実験用のカセットコンロです。安全装置つきで子どもでも扱いやすく、火力が強いため、実験時間の短縮にも役立っています」
【歴史】
・(昭和)聖徳太子 → <令和>厩戸皇子
■1万円紙幣などにも登場した聖徳太子は、じつは人の“名前”ではない。「歴史の研究が進むにつれ、聖徳太子という名前は、後世になって彼の功績を称えるために作られたものであることが明らかになっています。本来の名前は、『厩戸皇子(うまやどのみこ)』や『厩戸豊聡耳皇子(うまやどのとよとみみのみこ)』になります」
・(昭和)仁徳天皇陵 → <令和>大仙古墳
■全長約486m、日本最大の前方後円墳である仁徳天皇陵。「仁徳天皇が埋葬されているか定かではないため、地名の大仙が使われるようになりました。ちなみに、『大和朝廷』も実態は豪族の連合体で、朝廷を指す中央集権体制ではないため『ヤマト政権』に変更されています」
・(昭和)大化の改新は645年 → <令和>646年
■「『改新の詔』が発表されたのが646年の正月のため、歴史の正確性に基づいて変更されています。鎌倉幕府の成立も、源頼朝が征夷大将軍に任命されたのは1192年ですが、朝廷から守護・地頭を全国に置く権利が与えられて武士の政権が確立したのが1185年のため、変更されています」
・<令和>国宝・源頼朝の肖像画は“別人”
■「鎌倉時代の画家・藤原隆信による源頼朝の肖像画とされていましたが、制作年代や画風から、室町時代の人物を描いた可能性が指摘されています。そのため頼朝だと伝えられるとして『伝源頼朝像』と『伝』をつけるようになりました」
・(昭和)関ヶ原の戦いは、東軍・徳川家康と西軍・石田三成が戦った → <令和>西軍・毛利輝元
■「関ヶ原の戦いの西軍大将が石田三成から毛利輝元に変更になった理由は、輝元が豊臣政権の五大老のひとりで、中国地方の大大名として影響力があったためです。実際に戦の指揮を取ったのは三成で、輝元は政治的な役割を担っていました」
・指揮をした艦隊が人類初の世界一周航海を達成したのは……
(昭和)マゼラン → <令和>マガリャンイス
■「海外の人物の表記は、日本語での慣用的な表記でしたが、近年は現地語の発音に近い形で表記することが増えています。マゼラン→マガリャンイス(ポルトガル語に準拠)、リンカーン → リンカン(英語の発音に近い)などです」
・江戸時代にキリシタンを摘発するためにおこなわれたのは……
(昭和)踏絵 → <令和>絵踏
■「令和の教科書の表記で踏絵→絵踏になったのは、より実態に合った正しい表現にするためです。昭和の教科書では、絵を踏ませる行為を踏絵と記載していましたが、実際の歴史では『絵を踏ませる行為』と『踏まれる絵』で呼び方が異なっていました。つまり、絵を踏ませる行為が絵踏で、踏ませた対象物が踏絵となります」
・<令和>江戸時代の身分制度「士農工商」は、存在しなかった
■「江戸時代の身分制度は、士(武士)、農(百姓)、工(職人)、商(商人)の順で位が高かったと教科書で教えられてきました。それが近年の研究により、この身分制度は存在しなかったことが明らかになりました。武士が支配層でしたが、ほかの身分に上下関係はありませんでした」
・(昭和)日本最古の貨幣は「和同開珎」 → <令和>「富本銭(ふほんせん)」
■「1999年、奈良県飛鳥池工房遺跡で発見された富本銭が、日本最古の貨幣と認定されたため変更になっています」。7世紀ごろに鋳造された貨幣で、実際に流通したのか、まじない用として使われるだけに留まったのか、学説は分かれている
・最古の人類は……
(昭和)アウストラロピテクス → <令和>サヘラントロプス・チャデンシス
■「2001年、アフリカのチャドで頭蓋骨の化石が発見された『サヘラントロプス・チャデンシス』は約700万年前のもので、従来のアウストラロピテクスよりも300万年古いものでした」。2017年には、さらに60万年古いグレコピテクスの論文が発表されたが、証拠不十分のため研究が続いている
【地理】
・(昭和)日本には「4大工業地帯」がある → <令和>「3大工業地帯」がある
■「4大工業地帯が3大工業地帯に変わった理由は、北九州工業地帯の生産額が、京浜、中京、阪神工業地帯に比べ著しく低くなったためです。さらに、工業地域と称している東海、北陸、京葉と生産額が大差ない現状から『北九州工業地域』と表記されることが増えています」
【英語】
・(昭和)My name is … → <令和>I am …
■「My name isは古い言い方で、ネイティブで使う人はいません。そのため変更されています。また、姓名の順も2000年の国語審議会でローマ字表記を姓 → 名の順にすることが望ましいとなったこと、各国の文化を尊重するという国際的な流れを受けて変更になっています」
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)







