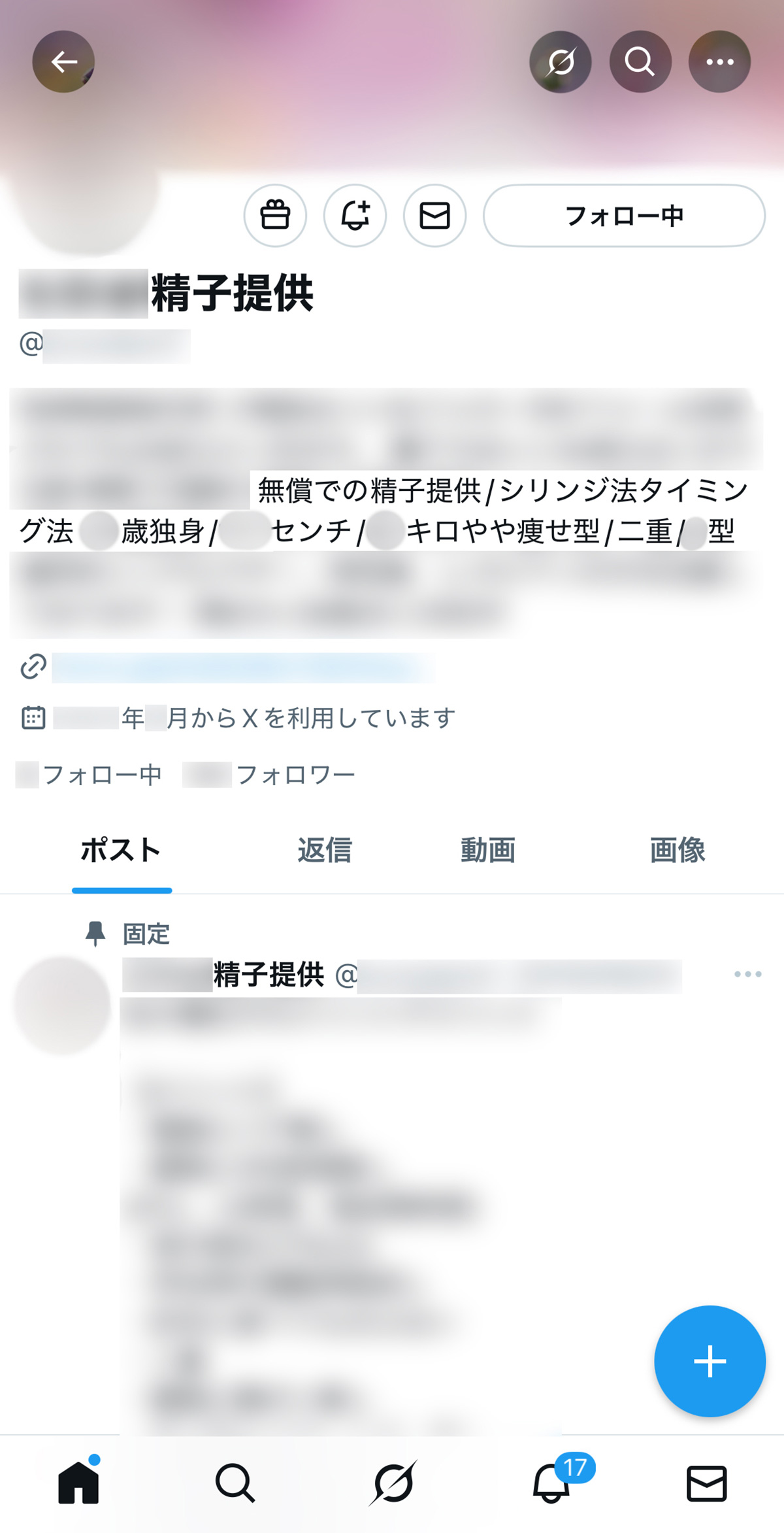
ある精子提供者のX
■150人に提供、生まれた子どもは80人
関西を拠点にする精子ドナー、蜃気楼(仮名)は、個人でありながら「精子バンク」を自称する。2008年からサイトやブログを通じて活動を開始した。
「日本でTwitterやFacebookが始まったのがちょうどそのころで、精子ドナーのアピールは皆無だったね。サイトもひと握りで、関西では私が最初。だから問合せがひっきりなしだったよ。勝手に真似されたりしたけど、弟子入りしてきた人もいる。メールのやり取りで信頼を置けたから、ノウハウを教えただけで実際には会ってないけどね」
40代後半になる蜃気楼。学歴などはいっさい明かさないが、大卒で準大手企業の社員だという。これまで150人弱に精子を提供し、妊娠に成功したのが50〜60人。複数の子どもを望む女性が多く、これまでに生まれた子どもは80人ほどという。
「提供法はシリンジがメインで5割を占め、次に人工授精が4割、タイミングは1割に過ぎない。人工授精用にそれだけ提供してきたのは、いくつかのクリニックとつながりができたから。非公式で、成婚カップル以外にも精子を提供するクリニックはけっこうあったんです。そこで精液を採取されるか、持ち込んで医師が雑菌を除去し、運動性の高い精子を選別するために洗浄・濃縮したうえで膣内へ注入するから、シリンジよりいくらか、妊娠の確率は高いとはいえる」
そして、2022年4月の不妊治療保険適用により、不妊にまつわる検査や治療のほとんどが保険でカバーされるようになった。自己負担額は1周期あたり5000円程度と、気軽に受けられる。しかし、これはあくまで夫婦間での設定で、第三者から精子提供を受けるとなると保険は適用されず、最低でもその10倍以上はかかる。次のステップの体外受精は、保険内の治療でも、採卵や顕微授精などプロセスを細かく踏むので、あっという間にそれ以上の金額に達する。
「だから、親戚や友人の精子なら黙認して、夫婦間のものとして人工授精をしてくれるクリニックもある。しかし、それよりずっと低コストで済むのが、自己で対応する個人間での精子提供。僕としてはそんな認識を広めたかった。妊活に大枚をはたいた、という話を聞くたびに、余計ね」
と蜃気楼は精子ドナーとなった動機を語る。信頼されるドナーを目指すには「安全第一」と、以前はクリニックで、最近ではネットでキットを入手し、性病チェックも怠らない。
■妻とは「オープン・マリッジ」に
だが、蜃気楼にはほかにも動機があった。20数年前に結婚し、子どもももうけたが、長男のみで止まった。以降は、子を望まない妻とセックスレスとなり、互いにほかにパートナーがいることを認め合う、オープン・マリッジの状態に。
「寂しさを紛らわす意味もあったかな。もっとたくさん、自分の子どもがほしかった。そんな思いを、精子のレシピエント(提供を受ける側)には託してますかね。相手は、初期にはシンママが多かったけれど、いまではセクシャル・マイノリティが半分以上。クリニックで、男性不妊の夫婦に提供したこともある。最近はアセクシャル(無性愛者)も多いね。希望者は、北は東北から南は沖縄までいますよ。そのために東京へ出てきたことも。それでも交通費はもらいますが、ほかはいっさい要求しません」
シリンジ法の場合、排卵予定日の前5日間と予定日当日、そして予定日の後1日を含め、7日間のうち3日以上おこなうのが普通だが、相手が近隣在住でない場合、“一発勝負”に賭けることになる。
「医学的には、射精から2時間以内におこなわなければならず、時間との戦い。相手が近所に住んでいるなら、自宅で蓋つきの採精容器に射精して渡せばいいですが、たいていは相手の自宅近くまで出向き、自分もどこかで射精するので、場所選びも重要ですね。僕は射精後30分以内と心がけていたので、カラオケボックスをよく利用しました。寝転べないと注入は難しいんです。衛生面に不安があるけど、多目的トイレもたまに使う。あそこなら介助用ベッドでできるから」
気温が低くても、高くても、精子は弱りやすいため、なるべく適温の20〜25℃に保つのも肝心だとか。
そして、提供相手で多かったのは看護師だという。ひとりで子育てができる経済状況にあるかどうかは、蜃気楼が相手に望む最低限の条件だ。
「だって、せっかく自分が精子を提供した子が育児放棄され、施設送りなんて考えたくもないから。むろん、相手とは可能な限り面談を重ね、認知はしない旨などを記した同意書をかわすのは、必須です」
■年に1度、誕生日に写真が
これまで80人近くの子どもが生まれている蜃気楼。“我が子”とはまったく関係を持たないのだろうか。
「『生まれたばかりの子に父親がないのは不安』だと、シンママの希望者に言われ、1、2歳までパパ役を務めたことは何度もありますよ。以降も、初詣に行ったりね。年に1度、誕生日などに写真を送ってくる相手も何人かはいて、大事に育てているとわかるとうれしいですね」
年齢もあって「いまはもう半ば引退状態」と語る蜃気楼。かつて年間10人はいた提供先も3人に減った。新規を受けないわけではないが、2、3人めを“同じ種”で望む相手が中心だという。となると、やはり父性が芽生えてしまうようだ。
■日本人のために精子バンクを立ち上げたカウンセラー
精子提供による出産は、日本では1949年が初だとされる。現在でも法律上の規制はなく、厚労省は婚姻関係にある夫婦に限り、第三者の提供精子を用いた人工授精(AID)を容認しているのが実情だ。そのうえで、日本産科婦人科学会が全国16の病院やクリニックを登録し、無秩序な提供を防ぐため、「同一提供者からの出生児は10人以内」「提供者は原則匿名」などと定めている。
ところが、超党派の議員連盟が重ねてきた立法化への動きが、ここへ来て活発化している。2025年2月には「特定生殖補助医療に関する法律案」が参議院に提出された。法案では、誕生する子どもがルーツを知る権利の保障のため、提供者の個人情報の保管や開示について定める一方、治療対象が法律婚の夫婦に限られる。また、営利的な精子の売買も禁じられる。
「この法案が通ってしまうと、海外の多くの営利的な精子バンクは日本の医療機関では利用できなくなります。法案のたたき台が初めて公表された2022年3月、当時、私が勤務していた世界最大の精子バンク『クリオス・インターナショナル』(本社・デンマーク)は日本進出計画を中断し、法案の成否が決まるまでの間、プロジェクトを凍結することになったんです」
と語るのは、東京駅にある「プライベートケアクリニック東京」東京院で不妊カウンセラーを務める、伊藤ひろみさん。伊藤さん自身、無精子症と診断された夫の欧州留学に帯同し、精子提供を受けて2人の子どもを授かっている。2019年2月、クリオス社の日本窓口の開設と同時にディレクターに就任した。だが、上記の法案の可決が見込まれるなか、日本で治療する日本の人々のため、非営利での精子バンク運営を目指して、伊藤さんは退職を決断した。
「法案に記載された、子どもがルーツを知る権利も、18歳以上の成人した子どもから請求があれば、その時点での提供者の意向で開示される情報が決まります。提供者の意向にかかわらず必ず開示されるのは、身長や血液型、年齢といった、提供者が特定されない情報のみ。結果的に、匿名のままとなる可能性が残ります」
伊藤さんは、子どもの知る権利を保障する「非匿名」での提供方法が重要だと考えていた。それは、子どもが大きくなってドナーが誰であるかを知りたくなったときに、提供者の名前、居住する都道府県、生年月日、連絡先を開示してもらえる仕組みである。伊藤さんも、非匿名での精子提供を受けている。
そこで、伊藤さんはクリオス社をやめる際、以前から知る、プライベートケアクリニック東京の小堀善友院長に相談。共同で、院内に日本初の非匿名精子バンクを創設し、2024年2月に現職に就いた。小堀院長は泌尿器科医として、無精子症の手術をたびたびおこなってきたので、精子提供の重要性を理解していた。
小堀院長は「すべての当事者が幸せになれるような、やさしい仕組みをつくりたい」という伊藤さんの志に共感。だからこそ、SNSを通じた個人間での精子提供は「リスクが多すぎる」と指摘する。
「『精子提供』で検索してヒットした140のウェブサイトを調べた結果、96.4%は安全ではないと判断されたとの、2021年6月に発表された文献もあります。基準をクリアした5つのウェブサイトのうち、3つは民間企業のもので、残る2つの個人サイトも提供者の情報が不明瞭で、安全とは言い切れないという結果でした」
医療機関では、感染症のリスクのない精液のみを凍結保存し、人工授精に用いる。産婦人科ではないプライベートケアクリニック東京・東京院では、精子を採取・凍結保存し、提携先の産婦人科に供給する。ところが、個人間の提供では。採取した精液をそのまま使用するので、その時点で健康に見える提供者に、何らかの感染症が潜伏している可能性は否めない。また、タイミング法で見知らぬ相手と性交に及ぶのも「勧められない行為」と小堀院長は語る。
今回の取材から、理由や事情はさまざまだが、精子提供への需要が高いことを肌で感じた。どんな手段が取られるかにかかわらず、ドナーにとっても希望者にとっても安心・安全な方法の確立と普及が望まれる。
取材/文・鈴木隆祐
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)







