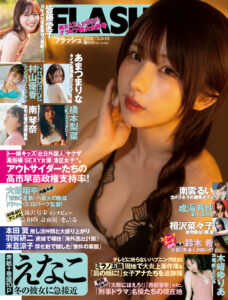みなさんは普段から数字を使った目標を立てているでしょうか。たとえば、2か月後までに3キロ痩せるとか、1日1万歩歩くとか、毎日の糖質摂取量を120グラムに抑えるとかです。私は体型維持のために、糖質制限をしています。これが達成できて「今月は頑張れたな」とか、反対に「今日は頑張れなかったな」となります。つまり、自分の頑張りを評価するにあたって、何らかの基準を作っているわけです。
目標を決めるとき、みなさんは何を基にするでしょうか。たとえばランニングなら、ネットで調べた数字を根拠にする人もいれば、これまで何度かランニングに挑戦した経験や一日のうちの使える時間などを基に計算する人もいるでしょう。これまでは1時間を目標にして断念していたから、今回は30分のランニングを毎日続けられるようにしようといった感じです。
これを企業に当てはめて考えると、ネットで調べて最適な水準を得ることは非常に困難です。しかし、これまでの経験に基づいて目標を設定することはありうるでしょう。たとえば、今年度は売上高100万円を達成したから、来年度は102万を目標に頑張ろうといったイメージです。
このとき気を付けるポイントが、事業環境の連続性です。つまり、今年と来年で事業環境が急に変わりまくることはなく、だいたい同じ状況だろうと考えて目標を置いているわけですね。その場合、今年度の反省を活かしたり、さらにスキルを磨けば来年はもっと良い結果を達成できると考えられます。
このように、事業環境が連続的でそれほど大きな変化がないと考える場合、過去の成果に基づいて目標を立てることは有効な手段だといえるでしょう。なぜなら、漠然とした目標を設定されるよりも、根拠のある目標の方が、頑張り方もわかりやすいからです。
■サボりますか? サボりませんか?
では次の思考実験をしてみましょう。
みなさんは4月から3月までの1年間の業績を基に、次の期間の報酬が決まる年俸制で働いているとします。契約はシンプルで、期初に立てた目標を超えたら100万円プラス、超えられなければ100万円マイナスです。目標は過去の業績を参考にして立てられます。昨年の売上高が115万円だったので、これに基づいて期初に立てた年間の売上高目標は120万円となっています。そしてあなたは12月末の時点で118万円の売上高を達成しています。
さて、あなたはこのあとの1月から3月まで、どのように仕事をしますか。ここで、「あと2万円だし、高い売上高を達成すると、来年度の目標が高くなっちゃうからちょっとサボろう」と考えた人が多いことを願いながら話を進めます。これが欲しかった回答です。
目標設定の観点からは、「過去の成果に基づいて目標が設定されるとき、達成時には目標を大きく引き上げられる一方、未達時には大きく引き下げられない」という議論があります。このような目標設定のことをラチェッティングといいます。
つまり、今回のケースで「サボる」と回答した人は、ラチェッティングを恐れて努力を節約したわけです。このように、ラチェッティングによって被評価者が努力を節約してしまう効果をラチェット効果とよびます。
過去の情報は、その人の能力やこれまでの頑張りを推測するのに有効ですが、これに頼ってしまうことによる負の側面も存在するわけです。とくに成果と報酬が結びつく場合には、目標を高く引き上げられすぎると報酬が得られないので、ラチェット効果がより強く生じる可能性が高まります。
しかし、だからといって完全にゼロベースで目標を立てると、途方もない目標や緩すぎる目標になって、従業員の努力を引き出すことができません。目標設定の難しさは、このバランスをどう保つかにあるといえます。
■ラチェッティングを抑制する方法
実はラチェット効果やラチェッティングを抑制する方法もいくつか提案されています。ラチェット効果を抑制するうえで大事なのは、今期の目標がその人の頑張りを引き出すために有効な水準になっていたかどうかです。
つまり、容易に達成できる目標なら途中で努力を節約してしまうし、困難すぎる目標ならあきらめて頑張らなくなってしまう、これがラチェッティングと組み合わさってラチェット効果が表われます。そのため、過去の情報を利用して適切な水準に目標を設定できれば、ラチェット効果を抑えることができます。
しかし、このちょうどいいラインを探すのは非常に難しいわけです。そこで考え出されたのが、相対的目標設定とよばれる方法です。ナバラ大学のカルメン・アランダらは、ある人の目標を設定するのに、ほかの人の情報を利用できる可能性を主張しました。
目標設定の難しさは、今回得られた成果がその人の頑張りによるものなのか、たまたま得られた成果なのかをわける難しさに起因します。つまり、売上高が高くなったのはたまたま取引先の機嫌がよかっただけで、自身の努力や能力によるものではない可能性もあるわけです。
過去の成果を使って目標が設定されるとき、この「たまたま」の要素をうまく排除することが難しくなります。つまり、本来は成果をみてその人の頑張りをうまく評価し、それに報いる形で報酬を与えたいのに、余分な要素があるせいで頑張りを引き出せる水準の目標設定が難しくなってしまう可能性があるわけです。
そのために有効になるのが相対的目標設定です。たとえば、自分がいる部署で、自分だけでなく部署全体の調子が悪く、目標が達成できなかったとしましょう。このときどう考えるでしょうか。もちろん、個々人の能力が原因になっている可能性は残ります。しかし、ほかの人も全員調子が悪いのなら、自分に責任のない外的な要因が影響している可能性を考えますよね。
たとえば、冷夏でアイスが売れないなどでしょうか。このとき、みんなが目標を達成できないのは、その人の努力のせいではありません。冷夏のせいです。このケースでは、「冷夏」のせいで「頑張っても無駄」となるわけですから、冷夏という自分に責任のない要素を省いて、目標を立てる必要があります。
逆にいえば、複数人の成果をみることで「冷夏のせいでどれだけ成果が落ちるか」という情報を抽出することが可能です。これによって、評価される人の能力や頑張りをより正確に推測でき、その能力の人が目一杯頑張って達成できる水準を推測できるようになります。
そうすると、その人がより達成できそうな目標を設定して、ラチェット効果による努力の節約を抑制できます。相対的目標設定では、ある人の目標を立てるのに、ほかの人の情報を利用してその人に対して効果的な目標を設定することになります。
実はこれ、相対的業績評価と似たような話です。相対的業績評価もこの話と同様に、評価される人の能力や頑張りを推測することに利用できます。評価される人に「あいつと比べるから、あいつより頑張れ」というのではなく、他者と比較することでその人自身の頑張りを推測することが、相対的業績評価の重要な役割です。
目標については「被評価者の達成できるギリギリの水準に設定するのがよい」という考え方があります。その人が提供できる最高の努力を組織の側が引き出せるなら、それに越したことはありません。
組織はいろいろな人のいろいろな仕事の組み合わせで成り立っているので、どこかでボトルネックが生まれると全体に悪影響を及ぼすこともあります。そのため、誰が何を管理できて、それに基づいてどのような目標を設定するかは組織にとって重要な問題です。
※
以上、濵村純平氏の新刊『評価と報酬の経営学 アイツの査定は高すぎる?』(光文社新書)をもとに再構成しました。なぜ役員報酬は高くなるのか、なぜ主観的な評価ばかりになるのか、身近な疑問から経営管理の真髄に迫ります。
●『評価と報酬の経営学』詳細はこちら
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)