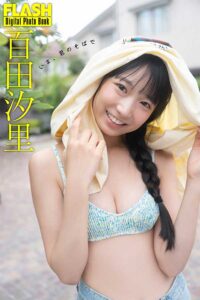長年の夢だった2008年北京オリンピック出場を逃した頃、村田は東洋大学の生活課で職員として働いていた。まだ1年目の新人である。
村田は高校時代から稀に見る選手としてボクシング界ではそれ相応の特別扱いをされてきたが、「大学職員」という立場では、いままでの輝かしいキャリアは通じなかった。リング上で相手をバタバタなぎ倒す技術や、その実績はまったく問われず、エクセルやワードといったパソコンの基礎技術こそが問われたのだ。村田はこの時代まぎれもない“半人前”だった。
「自分は特別ではない」
理屈ではわかっていても、理解するには時間がかかったと、後に村田は振り返っている。

大学では、ボクシング部で部員たちの指導に携わった。理論派の村田にとって、部員たちの悪い部分はキリがないほど挙げることができた。最初の頃の村田は、それをこと細かく指摘していたという。
ところがボクシングの指導は自分のトレーニングのようにはうまくいかない。部員たちは指摘されてすぐに修正できるわけもなく、チームをまとめるのにも苦労し、「部を辞めたい」ともらす部員も出てきた。

苦悩する中で村田が重要視するようになったのは「主体性」だった。口うるさく弱点を指摘するのではなく、時には黙って見守ることも始めた。すると部員たちは自主的に試行錯誤し、練習に取り組むようになった。「辞めたい」と言っていた部員もチームのために試合に出たいと志願するようになった。

今でもときどき東洋大学のボクシング部の練習に参加しているという。
「プロになってから強くなったと思っていましたけど、部活は部活でとんでもなくしんどい。無意識のうちに練習では手を抜くようになっていたんだなと気づかされます。人生、いつまでも勉強ですね」
大学職員の経験は人間・村田諒太の大きな糧になっているのだ。
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)