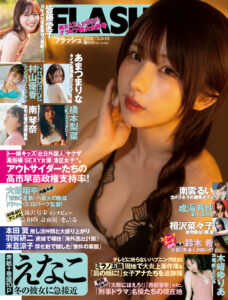秋といえばフルーツ狩りの季節だが……(写真・AC)
「苦い、もう1杯!」
サンマのはらわたで一献傾けるのは、この季節ならではの大人のゼイタク。この苦みが体にいいんだよな――。そんな思い込みを、管理栄養士の望月理恵子さんが否定する。
「サンマのはらわたの苦みと栄養の多寡は、無関係です!」
近年は不漁続きだったサンマだが、2025年は豊漁で前年の2倍以上の水揚げ。例年より大ぶりのサンマが店頭に並ぶ。だが、旬の味を楽しむはずが“都市伝説”に惑わされ、残念な晩餐を繰り広げていることになっていないだろうか。
「サンマはオス・メスどちらがおいしいかなど、さまざまな説があります。その答えは、はっきりとした結論のない△で、あまり気にする必要はないと思います」(望月さん・以下同)
ほかにも “食欲の秋” を台なしにする思い込みは多々ある。今回は望月さんの監修で、13の“審問”を作成。正しい知識を身につけ、スーパーに繰り出そう。
「サンマを選ぶときには、トングで袋に入れるタイプなら、持ち上げたときに体がピンと張るものを。パック入りなら、おなかがふっくらして、頭のつけ根から背中にかけて痩せていないものは脂が乗っています」
この季節は、総菜売り場でも塩焼きに手が伸びるが、刺身があればラッキー。ぜひ挑戦しよう。
「青魚には、動脈硬化など生活習慣病の予防に働くオメガ3脂肪酸が多く含まれ、刺身で食べるとおおいに恩恵を受けることができます。オリーブオイルと醤油を混ぜてかけると、カルパッチョのようにおいしく食べられますよ」
秋といえばフルーツ狩りの季節。果物も楽しみだ。
「梨のように、果物は皮のすぐ内側が甘みや栄養価が高いものが多いので、できるだけ皮を薄く剥くのがおすすめです。また、サツマイモやぶどうなど紫色のものには、アントシアニンやポリフェノールが多く含まれており、読書の秋で目を酷使したときにはぴったり。栄養価が高い、色の濃いものを選びましょう」
“都市伝説”に振り回されず、正しい知識で選ぶことこそが、本当のおいしさを楽しむ秘訣。それでは、秋の味覚の代表格であるサンマや青果について、間違えがちな “13の真実” を○・△・×で解説。思い込みがないかをチェックしてみよう。
【サンマ編】
■目が濁っていると鮮度が落ちている
→(△)白目、充血でも大丈夫 水揚げ時に生じることも
「目が透明だと鮮度がいい証拠ですが、濁っているからといって新鮮ではないとは限りません。サンマは一気に水揚げされるので、圧力で目がどうしても充血してしまったり、白目を剥いてしまったりすることがあるのです」(望月さん、以下同)
■大ぶりな今年のサンマ。どれもハズレなし?
→(×)“大きいことはいいこと”は大原則だが……
「身が大きくても、鮮度が悪くて痩せているものは食感がパサパサしがち。胴回りがしっかりしていて、頭の付け根から背中にかけてふっくらしているものを選びましょう。脂が乗っていておいしいですよ」
■口が黄色いほど鮮度がいい
→(○)水揚げされて3日ほどでだんだん濁ってくる
「新鮮なときは黄色いくちばしが、鮮度が落ちてくると茶色っぽくなります。サンマは傷みにくい魚といわれますが、はらわたあたりがダレていたり、持ち上げたときに張りがなく、ダラッとなったりする場合は要注意です」
■はらわたは苦いほど栄養がある
→(×)「良薬口に苦し」 と思う気持ちもわかるが……
「栄養の多寡と苦みは無関係です。サンマは胃がなく、体に排泄物が溜まりにくいため、本来ははらわたにも苦みが少ないんです。むしろ苦い場合は、鮮度が落ちて『アミン』という苦み成分が生成されている可能性があります」
■オス・メスでおいしさが違う
→(△)「メスがうまい」「オスだ」ネットの意見は真っ二つ
「下顎の先端が尖っているのがオス、丸みがあるのがメスといわれますが、見た目では判別は困難です。一般的に産卵後のメスは脂が乗っておらず、味が落ちるとされますが、店頭に並ぶものに優劣はほぼないでしょう」
【青果編】
■マツタケは傘が開いているほうが香りが強い
→(×)魅力的な見た目はいかにも高級そうだが……
「傘が大きく開いた立派なマツタケは、じつは香りがどんどん抜けている状態。一方、傘が閉じた段階ではまだ熟しておらず、香りは十分に立っていません。香りを求めるなら、“中開き”の状態を選ぶのがいいと思います」
■マツタケは凍らせると香りが落ちる
→(×)凍ったまま調理すれば閉じ込められた風味が開く
「マツタケの香りは、熱や時間の経過で抜けやすい一方、冷凍すると生の状態より風味がしっかり残ります。食べる際は、凍ったまま調理するのがおすすめ。冷凍すると香りが落ちると思われがちですが、逆なんです」
■果物によって美味しい場所が違う
→(○)甘いのはお尻、中心、それともヘタの近く?
「果物は、熟し方にパターンがあります。桃やりんご、バナナ、柿は、下から順番に糖分が蓄えられるため、お尻の部分が甘くなります。逆に、ぶどうは枝につながるヘタ側から栄養が入っていくので、上のほうが甘いんです。スイカやメロンは種の周囲に栄養が集中するため、中心部がいちばん甘くなります」
■ぶどうは買ってしばらく置いておいたほうが甘くなる
→(×)柔らかくなっているのは劣化しているだけです
「りんごや桃は、買って食べようとしても硬くて美味しくないことがありますよね。これらは収穫後、時間を置くことで『追熟(ついじゅく)』し、食べごろになります。勘違いしやすいのが、ぶどうや柑橘類。保管しているうちに柔らかくなっていきますが、張りがなくなって劣化しているだけ。購入後は早く食べましょう」
■干し柿にすると栄養価が増す
→(△)熟れるほど甘くなるため勘違いしがちだが……
「柿はキウイに匹敵するほどビタミンCが豊富ですが、熟すことで大幅に減ってしまうんです。一方、干し柿の場合は、ビタミンCは失われるものの、カリウムや食物繊維は濃縮され、効率よく摂取できます」
■シイタケは傘に栄養が集中している
→(×)傘と同じくらい栄養豊富な軸も料理に活用しよう
「シイタケは『傘』『軸』『石づき』に分かれていて、傘から下を捨ててしまう人も多いようです。軸にも傘と同じくらい食物繊維やビタミンB1、B2、旨み成分のグルタミン酸が豊富。食べられないのは石づきだけです」
■栗は冷蔵庫で保管すると甘くなる
→(○)甘~い栗とサツマイモ、保存方法は真逆だった
「栗は冷蔵庫で1カ月ほど保存すると、でんぷん質が糖に変わって甘みが増します。一方、同じ秋のスイーツ・サツマイモは、冷やすと味が落ちてしまいます。栗は冷蔵庫、サツマイモは常温と、保存法は真逆なんです」
■梨は中心部のほうが栄養が多い
→(×)いちばん甘いのは皮の近く…スティックにして丸ごと!
「種があるから “栄養が集まっていそう” と思われがちですが、梨は皮のすぐ内側がいちばん甘く、カリウムやポリフェノールなどが豊富に含まれています。皮ごとスティック状にカットして食べるのがおすすめです」
望月理恵子さん(管理栄養士)
健康検定協会理事長。食と健康に関する著書や講演多数。メディア出演も多い
![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)